障害者控除とは?4つの適用要件
障害者控除は、満85歳未満の障害者が相続人となった場合、その年齢に応じて相続税額から一定額を控除する制度です。 適用を受けるには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
- 相続や遺贈で財産を取得したこと
- 法定相続人であること
- ※遺言で財産をもらっただけの友人などは対象外です。
- 相続開始日に障害者であること
- ※原則として障害者手帳の交付を受けている人が対象ですが、申請中などの場合は医師の診断書等で認められることもあります。
- 日本国内に住所があること
85歳以上は対象外
この制度は「85歳になるまでの生活費を支援する」という趣旨のため、85歳以上の方は控除額が計算上0円となり、適用されません。
「一般障害者」と「特別障害者」の違いと控除額
| 区分 | 定義・対象となる手帳の等級(例) | 控除額の計算式 |
| 一般障害者 | 身体障害者手帳3級〜6級 精神障害者保健福祉手帳2級・3級など | (85歳 - 相続時の年齢) × 10万円 1 |
| 特別障害者 | 身体障害者手帳1級・2級 精神障害者保健福祉手帳1級 重度の知的障害など | (85歳 - 相続時の年齢) × 20万円 1 |
年齢計算の注意点(1年未満の端数処理)
計算において重要なのは年齢のカウント方法です。相続税法上、年齢の計算において1年未満の期間がある場合、それは「切り上げ」ではなく、期間計算としてフルに控除期間を確保する解釈が一般的です。
(補足: 実務的には「85歳に達するまでの年数」として計算され、例えば満40歳3ヶ月の場合、85歳までの期間は44年9ヶ月となりますが、数式上は「1年未満の端数は切り上げ」て計算期間を長く取る(つまり控除額を増やす)有利な取り扱いがなされます。例:85 – 40.25歳 = 44.75年 → 45年として計算。)
障害者控除の計算方法(一般・特別)
控除額は、障害の重さ(一般・特別)と、85歳までの残りの年数によって決まります。
計算式
一般障害者: (85歳 - 相続時の年齢) × 10万円 特別障害者: (85歳 - 相続時の年齢) × 20万円
【計算のポイント】 年齢計算において、1年未満の端数は切り捨てて計算します(結果として控除期間が1年長くなり、有利になります)。
- 例:40歳6ヶ月の場合 → 40歳として計算(85-40=45年分)
計算例:40歳の特別障害者(重度)の場合
- (85 - 40) × 20万円 = 900万円 この場合、本人の相続税から最大900万円まで差し引くことができます。
最大のメリット「扶養義務者への転用」
障害者控除の計算結果が、本人の相続税額よりも大きかった場合(控除枠が余った場合)、その余りを**「扶養義務者」の相続税から差し引く**ことができます。
【事例】
- 障害者本人(40歳・特別):相続税額 500万円、控除枠 900万円 → 本人の税金は0円。400万円の枠が余る。
- 親(扶養義務者):相続税額 1,000万円 → 余った400万円を親の税金から引く。 → 親の納税額は600万円に減額される。
扶養義務者の範囲
| 相続人の関係 | 同居(生計一)の場合 | 別居(生計別)の場合 |
|---|---|---|
| 配偶者・子・親 | ○ 扶養義務者とみなされる | ○ 扶養義務者とみなされる(直系血族・配偶者のため) |
| 孫 | ○ 扶養義務者とみなされる | ○ 扶養義務者とみなされる(直系血族のため |
| 甥・姪 | ○ 扶養義務者とみなされる | × 扶養義務者とみなされない |
税額0円なら申告不要?注意すべき落とし穴
障害者控除を使って相続税が0円になった場合、相続税の申告手続き自体が不要になるケースがあります。 (※配偶者控除や小規模宅地等の特例は、0円でも申告必須です。ここが大きく異なります)
ただし、以下の場合は申告が必要です。
- 他の特例(配偶者控除など)と併用して0円になった場合
- 余った控除枠を他の扶養義務者が利用する場合(申告書で転用を明記する必要があるため)
申請に必要な書類と手続き
申告が必要な場合(または念のため申告する場合)、以下の書類が必要です。
- 相続税申告書 第6表: 「未成年者控除額・障害者控除額の計算書」という専用の様式があります。
- 障害者手帳のコピー: 障害の等級や交付日を確認するため必須です。
- 医師の診断書(手帳申請中の場合): 相続開始時点で手帳が交付されていなくても、申請中であり、かつ医師の診断書でその時点での障害の状態が証明できれば認められる場合があります。
複雑な「家族配分」は『簡単相続ナビ』で解決
障害者控除には、「誰と誰が扶養義務者になるか」「余った控除枠を、父と母のどちらから引けば一家の税金が一番安くなるか」といった、高度な判断が求められます。
- 「別居している兄は扶養義務者に入る?」
- 「過去に父の相続で控除を使ったけど、今回の母の相続でも使える?(控除制限の計算)」
こうした複雑なパズルを解くために、高額な税理士報酬を支払う必要はありません。 **『簡単相続ナビ』**なら、家族構成と障害者情報を入力するだけで、システムが最適解を導き出します。
『簡単相続ナビ』のメリット
- 控除転用の自動最適化: 余った控除枠を、最も節税効果が高い家族へ自動的に割り振るシミュレーションが可能です。
- 要件の自動判定: 甥や姪が含まれる場合の扶養義務者判定や、過去の利用履歴に基づく制限額も自動計算します。
- 申告要否のチェック: 「本当に申告しなくていいのか?」の判定もシステムがサポートします。
「自分たちで賢く節税したい」 そうお考えの方は、まずは『簡単相続ナビ』で、家族全体の納税額がいくら下がるかを確認してみてください。






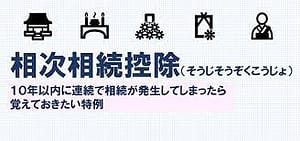



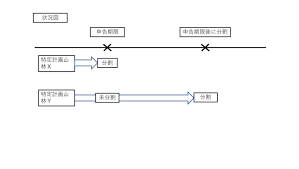
コメント