1. はじめに:相続税の「課税」と「非課税」
相続財産のすべてに相続税がかかるわけではありません。 国税庁のルールにより、**「非課税財産(ひかぜいざいさん)」**として相続税の計算から除外できるものがあります。 これらを正しく理解し、財産目録から適切に切り分けることで、無駄な税金を払わずに済みます。
本記事では、相続の知識がない方でも迷わず判断できるよう、非課税となる財産の具体例と、そもそも相続できない財産について解説します。
2. 相続税がかからない「非課税財産」リスト
以下の財産は、相続税の計算に含める必要がありません。
2.1 祭祀財産(さいしざいさん)
先祖を祀るための財産は、原則として非課税です。
- お墓関係: 墓地、墓石、墓碑
- 仏具関係: 仏壇、仏具、位牌、神棚、神体
【注意点】
- 純金製の仏像や、美術品として価値が高い骨董品など、投資対象や商品として所有しているものは課税対象となります。
- これらは「祭祀承継者(お墓を守る人)」が引き継ぐもので、遺産分割の対象にはなりません。
- 生前に購入済みであることが条件です。死後に遺産を使ってお墓を買っても、その購入費用は非課税にはなりません(ただし、購入したお墓自体は非課税です)。
2.2 生命保険金・死亡退職金の「非課税枠」
死亡保険金や死亡退職金は「みなし相続財産」として課税対象になりますが、以下の金額までは非課税です。
非課税限度額 = 500万円 × 法定相続人の数
例:相続人が3人(妻、子2人)の場合 500万円 × 3人 = 1,500万円までは非課税
2.3 公益事業や寄付に関するもの
- 寄付金: 相続した財産を、相続税の申告期限(死亡後10ヶ月)までに国や地方公共団体、特定の公益法人(認定NPO法人など)に寄付した場合、その分は非課税になります。
- 公益事業用財産: 宗教、慈善、学術などの公益事業を行う人が取得し、その事業に使うことが確実な財産。
2.4 その他
- 心身障害者扶養共済制度の給付金を受ける権利
- 幼稚園事業に使われていた財産(一定の条件を満たす場合)
3. 相続税から引ける「マイナスの財産」と「葬式費用」
課税対象となる財産から差し引くことで、相続税を安くできる項目です。
3.1 債務控除(借金など)
亡くなった人が残した借金や未払金は、遺産総額から差し引けます。
- 借入金(住宅ローン、カードローン)
- 未払いの医療費
- 未払いの税金(住民税、固定資産税など)
- 未払いの水道光熱費
3.2 葬式費用
お葬式にかかった費用も、遺産総額から差し引くことができます。
- 引けるもの: 通夜・告別式の費用、火葬料、埋葬料、お布施、読経料、遺体の搬送費用
- 引けないもの: 香典返し、法事(初七日・四十九日)の費用、墓地・仏壇の購入費用
【ポイント】 領収書がないお布施なども、メモ(支払日、支払先、金額)を残しておけば控除が認められる場合があります。
4. そもそも「相続できない財産」とは?
故人が持っていた権利でも、相続人に引き継げないものがあります。これらは「一身専属権(いっしんせんぞくけん)」と呼ばれ、本人の死亡とともに消滅します。
- 資格・免許: 医師免許、運転免許、税理士資格など
- 受給権: 生活保護受給権、養育費の請求権、年金受給権(※未支給年金は遺族が請求できますが、相続財産ではなく遺族の所得になります)
- 代理権: 雇用契約上の地位、身元保証人の地位
5. まとめ:正しい切り分けで節税とトラブル回避を
財産整理の際は、以下の手順で切り分けましょう。
- プラスの財産を洗い出す(預金、不動産など)
- そこから**「非課税財産」**(お墓、保険金の非課税枠など)を除外する
- さらに**「マイナスの財産」と「葬式費用」**を差し引く
- 残った金額が**「基礎控除(3,000万円+600万円×相続人数)」**を超えているか確認する
この計算を間違えると、無駄な税金を払ったり、逆に申告漏れでペナルティを受けたりする可能性があります。
**『簡単相続ナビ』**なら、
- 財産の種類を選ぶだけで、課税・非課税を自動判定
- 保険金の非課税枠や基礎控除も自動計算
- 「財産目録」として一覧表を簡単に作成
複雑なルールを覚えなくても、画面の案内に従うだけで正確な財産整理が可能です。 まずは無料シミュレーションで、ご自宅の相続税がいくらになるか確認してみませんか?



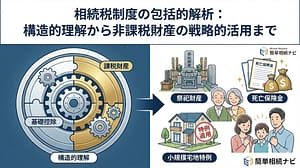



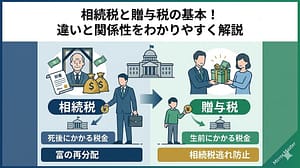

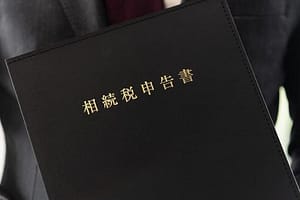

コメント