「実家の名義変更、まだしていなかった…」 そんな方に衝撃的なニュースです。2024年(令和6年)4月1日から、相続登記(不動産の名義変更)が法律で義務化されました。
これまで任意だった手続きが義務となり、正当な理由なく放置すると**「10万円以下の過料」というペナルティが科される可能性があります。 しかも、この法律は「過去に相続した不動産」にも適用される(遡及適用)**ため、現在すでに名義変更していない土地や家を持っている方も対象です。
本記事では、義務化の詳しい内容と期限、罰則を回避するための新制度「相続人申告登記」、そして自分で相続登記を行うための具体的な手順を専門家が解説します。 期限ギリギリで慌てないよう、今すぐ確認しましょう。
【2024年4月開始】相続登記の義務化と「10万円以下の過料」
近年、所有者が不明の土地が増加し、公共事業や災害復旧の妨げになる「所有者不明土地問題」が深刻化しています。これを解消するため、法律が改正され、相続登記が義務化されました。
義務化の3つのポイント
- 開始日: 2024年(令和6年)4月1日からスタート
- 期限: 不動産の取得を知った日から3年以内
- 罰則: 正当な理由なく怠ると10万円以下の過料
【最重要】「過去の相続」も義務化の対象です
今回の法改正で最も注意すべき点は、「施行日(2024年4月1日)より前に相続した不動産」も義務化の対象になるということです。 「昔のことだから関係ない」では済まされません。
- 2024年4月1日以降に発生した相続: 「知った日」から3年以内
- 2024年4月1日以前に発生した相続: 2027年(令和9年)3月31日までに登記が必要
現在、名義変更をしていない不動産がある方は、2027年3月末がデッドラインとなります。猶予期間があるうちに手続きを進めましょう。
相続登記をしないとどうなる?放置する3つのリスク
義務化されたからといって、「バレなければいい」と放置するのは非常に危険です。過料以外にも、実質的なデメリットが発生します。
1. 10万円以下の過料(ペナルティ)
法務局から催告が届いても手続きをしない場合、裁判所の判断により10万円以下の過料が科されます。これは「前科」にはなりませんが、無駄な出費であることに変わりはありません。
2. 不動産の売却や担保設定ができない
亡くなった人の名義のままでは、不動産を売却したり、リフォームローンの担保に入れたりすることが一切できません。「売りたい」と思った時にすぐ売れず、チャンスを逃すことになります。
3. 「数次相続」で権利関係が泥沼化する
登記を放置している間に、次の相続(数次相続)が発生すると、ネズミ算式に相続人が増えていきます。 当初は兄弟2人だけで話し合えばよかったものが、放置した結果、面識のない親戚10人以上と話し合わなければならなくなるケースも珍しくありません。こうなると、手続きの難易度と費用は跳ね上がります。
【新制度】間に合わない時の救済策「相続人申告登記」
「遺産分割協議がまとまらない」「相続人が多すぎて書類が集まらない」 このように、3年以内に登記ができない事情がある場合、新しく作られた**「相続人申告登記」**という制度を利用すれば、とりあえず過料を回避できます。
相続人申告登記とは?
「私はこの不動産の相続人です」と法務局に申し出るだけの簡易的な手続きです。
- メリット: 相続人が単独で申請できる(他の相続人の協力不要)。添付書類が戸籍謄本のみで簡単。とりあえず登記義務を果たしたことになる(過料回避)。
- 注意点: あくまで「報告」であり、正式な名義変更(権利の取得)ではありません。不動産を売却するには、後日改めて遺産分割協議を行い、正式な相続登記をする必要があります。
自分でできる?相続登記の手続き5ステップ
相続登記は司法書士に依頼するのが一般的ですが、時間と手間をかければ自分で行うことも可能です。
ステップ1:必要書類の収集
まず、以下の書類を集めます。これだけで数千円〜数万円の費用がかかる場合があります。
- 被相続人(亡くなった人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等
- 相続人全員の現在の戸籍謄本
- 相続人全員の印鑑証明書
- 固定資産評価証明書(最新年度のもの)
ステップ2:遺産分割協議書の作成(※ここが最難関)
実は、登記申請そのものより難しいのがこのステップです。 「誰がどの不動産を相続するか」を相続人全員で話し合い(遺産分割協議)、合意した内容を**「遺産分割協議書」**という書面にまとめ、全員の実印を押す必要があります。
この協議書がないと、法定相続分以外での登記はできません。
ステップ3:登記申請書の作成と費用の計算
法務局のHPから様式をダウンロードし、申請書を作成します。 この際、登録免許税(固定資産評価額 × 0.4%)を計算し、収入印紙を購入して貼付します。
ステップ4:法務局へ申請
不動産の所在地を管轄する法務局へ、書類を提出します(窓口持参、郵送、オンライン)。
ステップ5:登記完了・権利証の受け取り
不備がなければ1〜2週間で完了し、「登記識別情報通知(いわゆる権利証)」が発行されます。
司法書士に頼む?自分でやる?
- 司法書士に依頼する場合:
- 費用相場: 7万円〜15万円程度(登録免許税などの実費は別)
- メリット: 確実で手間がない。複雑なケース(数次相続など)も対応可能。
- 自分でやる場合:
- 費用: 実費のみ(数千円〜数万円)
- デメリット: 平日に役所や法務局へ行く必要がある。書類の不備で何度もやり直しになるリスクがある。
2026年からは「住所変更登記」も義務化へ
相続登記に続き、2026年(令和8年)4月からは、住所や氏名が変わった時の変更登記も義務化されます。 こちらも「変更から2年以内」に行わないと、5万円以下の過料の対象となります。引越しをして住所が変わっている方は、早めの手続きをおすすめします。
まとめ:登記の前に「誰が相続するか」を決めよう
相続登記の義務化は、ペナルティを避けるためだけでなく、あなたの大切な資産を守るための制度です。 特に「過去の相続分」も対象になるため、2027年の期限に向けて今すぐ動き出す必要があります。
『簡単相続ナビ』で遺産分割協議書をスムーズに作成
相続登記の手続きで最もつまずきやすいのが、**「誰が不動産を相続するか決まらない(遺産分割協議)」ことと、「遺産分割協議書の作成方法がわからない」**ことです。
話し合いがまとまらなければ、いつまで経っても登記はできません。
当社の**『簡単相続ナビ』**なら、不動産や預貯金を含めた遺産分割のシミュレーションが誰でも簡単に行えます。 「長男が不動産を継ぐ代わりに、次男には現金を多く渡す」といった代償分割の計算も一瞬で完了。さらに、合意した内容を反映した「遺産分割協議書」もシステム上で作成可能です。
高額な専門家報酬を払う前に、まずはご自身で「納得のいく分割案」を作ってみませんか?
【補足:用語集】
※本文中では読みやすさを優先し割愛しましたが、参考までに用語を解説します。
- 抵当権: 住宅ローンなどを借りる際、不動産を担保にする権利。
- 表題登記: 建物を新築した際などに行う、物理的状況(所在や面積)の登録。
- 所有権移転登記: 売買や相続で持ち主が変わった時に行う記録。いわゆる「名義変更」。


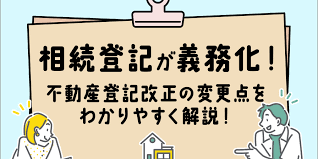






コメント