相続税の「計算」と「申告」は自分でできる?
「相続税がかかるのか知りたい」 「申告の手続きはどう進めればいいの?」
大切なご家族が亡くなり、悲しみの中にいる時でも、相続の手続きは待ってくれません。特に相続税の申告は**「10ヶ月」**という期限があり、遅れるとペナルティが発生するため、早めの着手が重要です。
この記事では、相続税の計算の仕組みと、申告までの具体的な手順を、専門用語を極力使わずに解説します。 また、複雑な計算を簡単に行い、専門家への依頼費用を節約する**「賢い申告方法」**についてもご紹介します。
1. ステップ1:相続税の計算方法(いくらかかるの?)
まず、「自分には相続税がかかるのか?」「いくら払うのか?」を知るための計算の流れを見ていきましょう。
相続税の計算は、大きく分けて以下の3段階で進みます。
① 遺産総額を出す(資産価値の計算)
亡くなった方が持っていた財産(不動産、預貯金、株など)をすべてリストアップし、それぞれの「相続税評価額(資産価値)」を計算して合計します。 ※ここが最も難しく、計算ミスが起きやすいポイントです。
② 基礎控除を引く(足切りラインの確認)
遺産総額から、誰でも使える「基礎控除額」を差し引きます。
基礎控除 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)
遺産総額がこの金額以下であれば、相続税は0円で、申告も不要です。
③ 税率をかけて税額を出す
基礎控除を超えた部分に対して、所定の税率(10%〜55%)をかけて税額を算出します。ここからさらに「配偶者控除」などを引いて、最終的な納税額が決まります。
2. 複雑な計算は『簡単相続ナビ』におまかせ
「不動産の評価額なんてわからない…」 「計算式が難しくて間違えそう…」
そう思われた方もご安心ください。ミラーマスター合同会社が運営する**『簡単相続ナビ』**を使えば、誰でも簡単に正確な計算が可能です。
- 資産価値の自動算出: 難しい土地の評価なども、ガイドに従って入力するだけ。
- 税額シミュレーション: 基礎控除や特例を考慮した「実際の税額」が瞬時にわかります。
- 自分だけの財産目録: 入力したデータはそのまま財産リストとして活用できます。
まずは無料シミュレーションで、「申告が必要かどうか」だけでもチェックしてみましょう。
3. ステップ2:相続税の申告手順(どう手続きするの?)
計算の結果、申告が必要だとわかったら、以下の手順で手続きを進めます。
① 必要書類の収集(〜2ヶ月目)
申告には多くの書類が必要です。役所や銀行で早めに集めましょう。
- 戸籍謄本: 被相続人と相続人全員分(出生から死亡まで連続したもの)
- 残高証明書: 銀行や証券会社から発行してもらう
- 不動産関係: 登記簿謄本、固定資産税評価証明書など
② 申告書の作成(〜8ヶ月目)
集めた資料と計算結果を基に、税務署提出用の「相続税申告書」を作成します。 第1表から第15表まであり、財産の種類や特例の適用に合わせて記入します。
③ 税務署へ提出・納税(10ヶ月以内)
被相続人(亡くなった方)の住所地を管轄する税務署へ申告書を提出し、税金を納付します。 期限は「亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」です。 1日でも過ぎると「延滞税」などがかかるので注意が必要です。
4. 申告は「自分」でやる?「専門家」に頼む?
相続税の申告は、自分で行うことも可能ですが、専門知識が必要です。 状況に合わせて、最適な方法を選びましょう。
ケースA:自分で申告する(コスト最安)
- 向いている人: 遺産が預貯金メインで少ない、遺産分割で揉めていない、時間に余裕がある。
- 方法: 『簡単相続ナビ』で作成した財産目録や計算結果を元に、国税庁のサイト等を使って申告書を作成します。
ケースB:税理士に依頼する(安心・確実)
- 向いている人: 土地などの不動産が多い、遺産総額が大きい、忙しくて時間がない。
- 注意点: 報酬相場は「遺産総額の0.5%〜1.0%」と高額になりがちです。
【おすすめ】『簡単相続ナビ』+専門家のハイブリッド活用
「税理士に頼みたいけど、費用は抑えたい」という方には、『簡単相続ナビ』で計算したデータを持って税理士に相談する方法がおすすめです。
税理士費用の多くは「財産調査」や「計算作業」の手間賃です。 事前に『簡単相続ナビ』で財産目録を作成し、計算のシミュレーションまで済ませておけば、税理士の作業負担が減り、報酬を安く抑えられる可能性があります(※依頼内容による)。
※注意:相続税の申告代行ができるのは「税理士」だけです。行政書士等は申告書の作成代理ができませんのでご注意ください。
まとめ
- 計算: 遺産総額から基礎控除を引き、税率をかける。
- 期限: 相続開始から10ヶ月以内に申告・納税が必要。
- ツール活用: 複雑な計算は『簡単相続ナビ』を使えば、初心者でも正確に行える。
- 賢い申告: ツールで準備を整えてから税理士に依頼すれば、費用対効果が最大化する。
相続税の申告は、準備が9割です。『簡単相続ナビ』を上手に活用して、期限内にミスのない申告を目指しましょう。


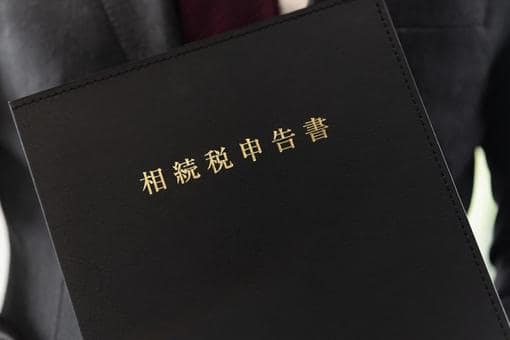
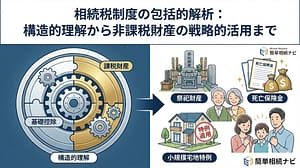




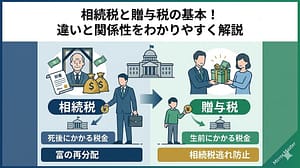


コメント